賃借人の要望に沿って建築され、他の用途に転用することが困難である建物について、 賃貸人が将来にわたり安定した賃料収入を得ること等を目的として、3年ごとに賃料を増額する旨の特約を付した賃貸借契約が締結された場合において、賃料減額請求の当否を判断するに当たり、専ら公租公課の上昇及び賃借人の経営状態のみを参酌し、借地借家法32 条1項所定の他の重要な事情を参酌しないまま、賃借人がした賃料減額請求の行使を否定 した原審の判断には違法があるとされた事例
(最高裁 平成17年3月10日判決 破棄差戻 金 融法務事情1746号126頁)
【判決】
借地借家法32条1項の規定は、強行法規であり、賃料自動改定特約等の特約によってその適用を排除することはできないものである(最判平15.6.12、平15.10.21、平15.10.23等参照)。
そして、同項の規程に基づく賃料減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、同項所定の諸事情のほか、賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべきである(前記最判平 15.10.21、平15.10.23等参照)。
本件賃貸借契約の基本的内容は、YがXに対して本件建物を使用収益させ、XがYに対してその対価として賃料を支払うとい うもので、通常の建物賃貸借契約と異なるものではない。
したがって、賃料減額請求の当否を判断するに当たっては、諸般の事情を総合的に考慮すべきであり、賃借人の経営状態など特定の要素を基にした上で、 独自の基準を設けてこれを判断することは許されないというべきである。
原審は、専ら公租公課の上昇及びXの経営状態のみを参酌し、土地建物の価格等の変動、近傍同種の建物の賃料相場等総合考慮すべき他の重要な事情を参酌しないまま、賃料減額請求権の行使を否定したものであって、その判断は借地借家法32条1項の解釈適用を誤ったものというべきである。
以上によれば、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決は破棄を免れない。賃料減額請求の当否、相当賃料額等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻す。
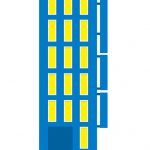






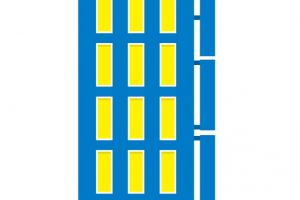



コメントを残す