はじめに
相続によって土地や建物を取得した際、多くの方が悩むのが「この不動産の取得価格は一体いくらと考えればいいのか」という点です。被相続人が取得した時の売買契約書があれば、それに基づいて考えればよいですが、売買契約書が存在しない場合には、税務上の扱いに困ることが度々あります。
特に問題となるのは譲渡所得税の計算です。もし取得価格が不明のまま処理を進めてしまうと、本来よりも不利な課税を受けたり、余計な納税義務を負担する可能性があります。
そこで重要になるのが、不動産の適正な評価を専門的に行える「不動産鑑定士」の存在です。本稿では、取得価格が分からないままでいるデメリットを整理しつつ、その解決のために鑑定士へ相談する意義を考えていきます。
1-1.将来の譲渡所得税計算に不可欠
相続によって取得した不動産を将来売却する場合、譲渡所得税の計算で必要になるのが「取得費」です。式にすると次のようになります。
-
譲渡所得 = 譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)
ここで「取得費」が不明の場合、やむなく**概算取得費(原則譲渡価格の5%)**で計算することになります。これが大きな問題を生みます。
たとえば、相続で取得した土地を2,000万円で売却したとしましょう。取得費が不明のため概算の「5%=100万円」として計算すると、差し引かれるのはわずか100万円だけ。結果として課税の対象となる譲渡所得は1,900万円にも上り、高額な税負担となります。
仮に専門的鑑定等で「当時の取得価格相当が1,800万円」と立証できれば、譲渡所得は200万円に圧縮でき、税額は大幅に下がります。この差額は数百万円にも及ぶことが多く、「取得価格が分からない」ことがいかに大きな不利益につながるかが分かるはずです。
1-2.「取得価格を把握していない」ことによる税法上のデメリット
-
譲渡所得税の過大計算
取得費不明のため概算5%方式を用いると、売却益が実態より大幅に大きく算定され、余計な税金を支払うことになる。 -
相続税の申告で不利な評価となる可能性
不正確な評価額で申告すると、過大課税につながり、場合によっては税務署から指摘・更正を受けるリスクもある。 -
二重課税的な不利益
相続時に高めの評価で相続税を支払ったにもかかわらず、譲渡時に取得費を認められず再び重く課税される「二重の不利益」が生じる場合がある。 -
相続人間のトラブル
評価が曖昧だと、遺産分割で「高い土地を安く見積もって不公平だ」といった不満が噴出し、親族間の不和につながる。
2.不動産鑑定士に相談する意義
では、この問題を解決するにはどうすべきでしょうか。最大のポイントは「客観的に説明できる適正価格を求める」ことです。ここで頼りになるのが不動産鑑定士です。
2-1. 適正な時価評価を提示できる
不動産鑑定士は、不動産の価格に関する唯一の国家資格者であり、地価公示・地価調査などの公的評価も担っています。法律や市場要因を踏まえて「適正な時点の価格」を算出できるため、税務申告や相続分割調整の根拠資料として高い信頼性を持ちます。
2-2. 「取得費相当額」として立証できる
相続によって取得した不動産では、実際の購入価格が存在しないため「亡くなった時点の時価」を基準に取得費を見積もることが一般的です。不動産鑑定士の評価書は、これを合理的に説明する資料として税務署に対しても有効に働きます。
2-3. 税理士との連携がしやすい
相続税や譲渡所得税の申告は税理士が行いますが、その前提となる資産評価は鑑定士の役割です。税理士と鑑定士が連携することで、法令遵守しつつ依頼者に最も有利な形で税務申告を行えます。
2-4. 紛争防止・合意形成の材料になる
相続人間で意見対立が生じた場合、第三者の専門家による鑑定評価は公正中立な基準となり、話し合いを円滑に進める助けになります。裁判や調停となった場合も、鑑定評価書は重要な証拠資料として採用されることがあります。
まとめ
相続で取得した不動産の「取得価格」を把握していないままでは、税法上さまざまなデメリットが生じます。特に譲渡所得税の計算においては、概算取得費方式を採用せざるを得なくなると、数百万円単位の過大課税が発生しかねません。また、相続税申告や遺産分割交渉の場面でも、不正確な評価は不利や紛争の原因となります。
この不安を解決する唯一の方法は、不動産鑑定士に相談し、客観的かつ合理的な評価を得ることです。不動産鑑定士が作成する鑑定評価書は、税務上の根拠資料として有効であるとともに、相続人間の合意形成にも力を発揮します。
取得価格の不明確さは、相続人にとって見えにくい「将来の落とし穴」です。早い段階で専門家に相談することが、不要な税負担や争いを防ぎ、不動産を守り資産を正しく承継するための最善策になるのです。
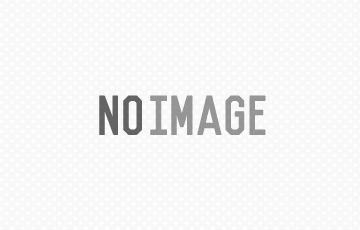



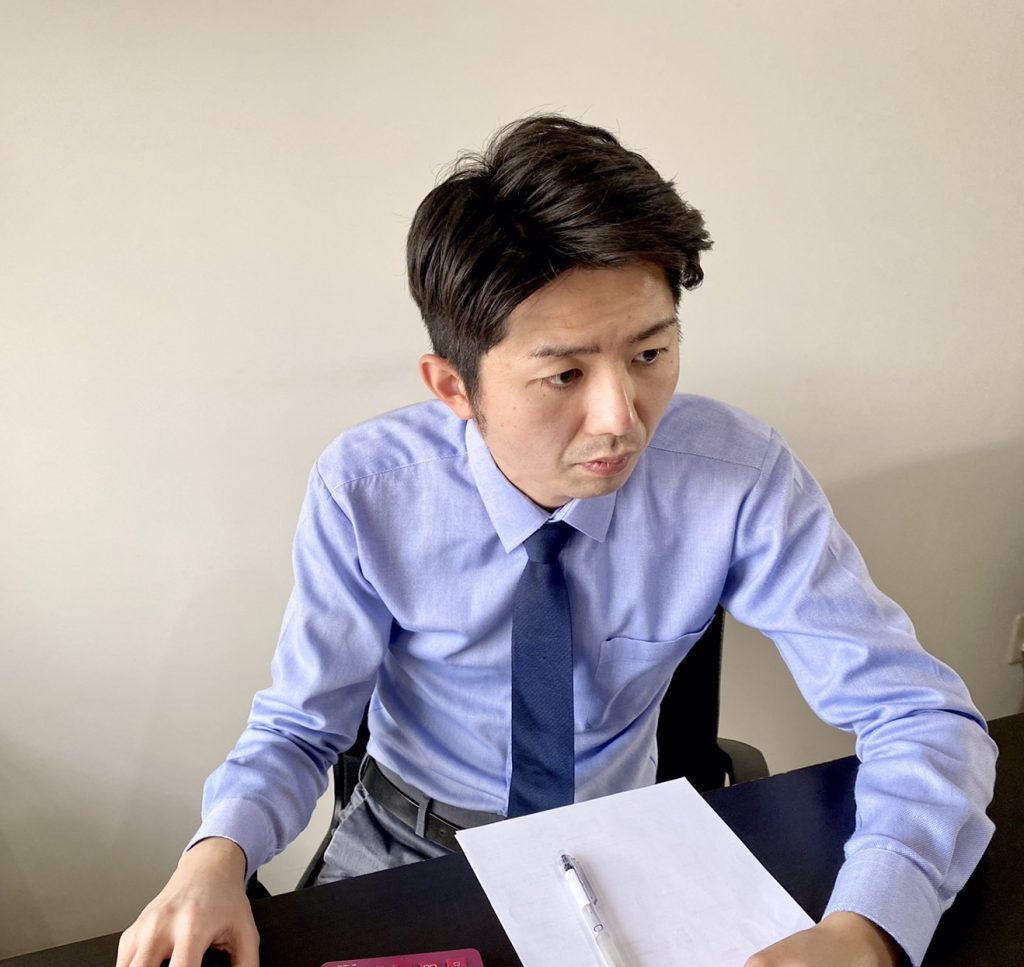
コメントを残す