弊社では、建物の経済的残存耐用に関するレポート(意見書)を発行しております。内容は次のようなものです。
1.実地調査時の概要
今回調査の対象となった不動産は、実査日時点において全ての住戸が賃貸に供されていることを確認いたしました。これは物件の稼働率が非常に高く、安定した賃貸需要が継続していることを示す重要な指標です。また、現地調査では1部屋の室内について直接確認いたしました。
室内の確認においては、入居者による日常的な使用状況に特段の問題は見受けられませんでした。壁面や床、天井などの内装部分についても、著しい損耗や汚損はなく、通常の生活使用による経年変化の範囲内に収まっていると判断されます。加えて、水回り設備や電気設備等のインフラ部分についても、機能上の不具合や安全上の懸念点は認められませんでした。
建物外部についても詳細に観察を行った結果、建物本体の傾きや基礎部分の沈下、外壁の亀裂、屋根からの雨漏り等、構造的な損傷や重大な劣化は確認されませんでした。特に、雨漏りや傾きといった現象は建物の寿命を大きく左右する要素であり、これらが認められないことは、建物の維持管理が適切に実施されている証左といえます。
維持管理状況については、屋根、外壁等の修繕が定期的に行われている形跡があり、建物全体として経年相応の状態を保っているものと評価されます。建物には目立った破損や汚損はなく、管理体制の良好さがうかがえました。築年数に応じた経年劣化は当然見受けられるものの、これが資産価値や賃貸運営に直ちに悪影響を及ぼすレベルではないと判断できます。
以上のとおり、対象不動産は現状においても高い賃貸稼働率と良好な維持管理状態を維持しており、今後も安定した運用が期待できる資産であると評価します。
2.「法定耐用年数=経済的耐用」ではないことの説明
次に、木造建物の法定耐用年数は一般的に22年とされていますが、これはあくまで税法上の減価償却計算の基準であり、実際の使用可能年数や寿命とは異なります。現実には、築40年を超えても適切なメンテナンスやリフォームを施すことで、十分に安全かつ快適に使用を継続できるケースが多く存在します。
実際、国土交通省の資料によれば(※)、非住宅建築物であるものの、維持管理の状態次第では建物の耐久性が50年以上となる旨が示されております。
(※)“評価対象建築物の耐久性に関しては、構造躯体の内部への雨水の浸入の防止、雨水の浸入があった場合の速やかな排出並びに雨水が浸入し滞留した場合の構造躯体への防腐処理及び防蟻処理を施すことが重要であることに鑑み、評価対象建築物について、これらの措置が適切に講じられていることをもって、一定の耐久性を有する建築物であることを評価する。この場合において評価すべきものは、評価対象建築物の構造躯体等を構成する部材の劣化のしにくさとする。この基準に適合する評価対象建築物に要求される水準は、通常想定される自然条件及び維持管理条件の下において、当該建築物が限界状態に至るまでの期間が 50 年以上となるために必要な構造躯体等を構成する部材の劣化現象を軽減する対策が講じられていることとする。“
ほかにも、木造のハウスメーカーの保証では、最大保証期間が20~30年のメーカーが標準的ですが、手厚い会社では建物がある限り永年保証というメーカーも存在します。
このように、木造であっても、長期の使用が期待できるとされております。つまり、築●年を経過している木造建物であっても、適切な維持管理がなされていれば、さらに●年以上の居住や利用が十分に可能です。
また、実際の市場でも築30~40年の木造住宅がリフォーム対象として流通し、古民家再生などの形で再び長期間使用される事例も増えています。これは、木造住宅の構造体そのものが健全であれば、設備や内装を更新することで新築同様の快適性を維持できることを示しています。
さらに、設備や内装についても、耐用年数10年程度を目安に、定期的な更新や修繕を行うことで、建物全体の寿命を延ばすことが可能です。たとえば、給排水や衛生設備、ガス設備、内装工事などは15年ごとに見直すことで、建物の機能性と安全性を長期にわたり確保できます。
このように、「現在も使用している」という事実は、その建物が物理的・機能的に十分な耐久性を有していることの証拠であり、今後も適切なメンテナンスを続けることで、さらに●年以上の使用が現実的であるといえます。
3.銀行融資の事実
不動産投資市場においては、木造で築●年を超えるアパートであっても、銀行が15~20年近い長期融資を実行する実例が数多く存在します。とくに信用金庫や地方銀行では築●年超の木造アパートに対し、耐用年数を大きく超える期間の融資が実現しています。
一般的に木造アパートの法定耐用年数は22年ですが、実際にはこの年数を超えても、金融機関によっては土地の評価や投資家の属性、共同担保の有無などを総合的に判断し、柔軟に長期融資を認めるケースが増えております。
このように、築古木造建物でも投資家の戦略や金融機関の方針次第で、20年近い長期融資を受けられる市場が形成されております。
これらの実査結果を総合的に勘案すると、対象建物は築40年を超えているものの、現時点では十分な機能性と安全性を維持しており、今後も適切な維持管理が継続されることが想定されるため、建物の経済的残存耐用年数を●年と判断いたしました。
まとめ
弊社ではこのようなレポートを発行し、実際に融資時の耐用年数が延長した実例がございます。ご相談はお気軽にお問い合わせください。
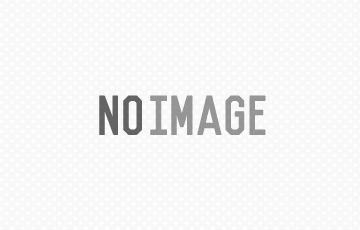
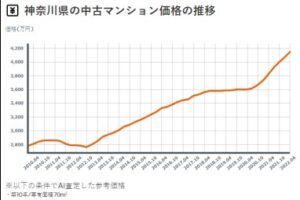
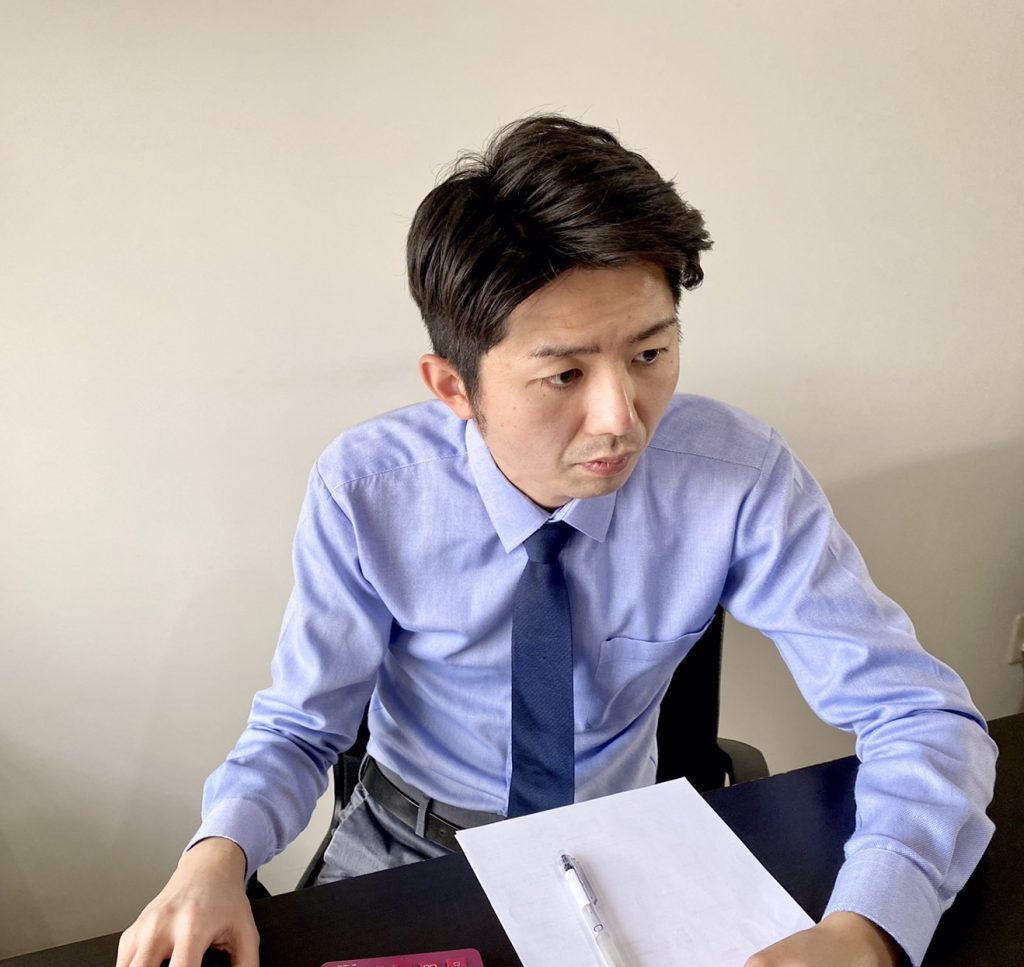
コメントを残す